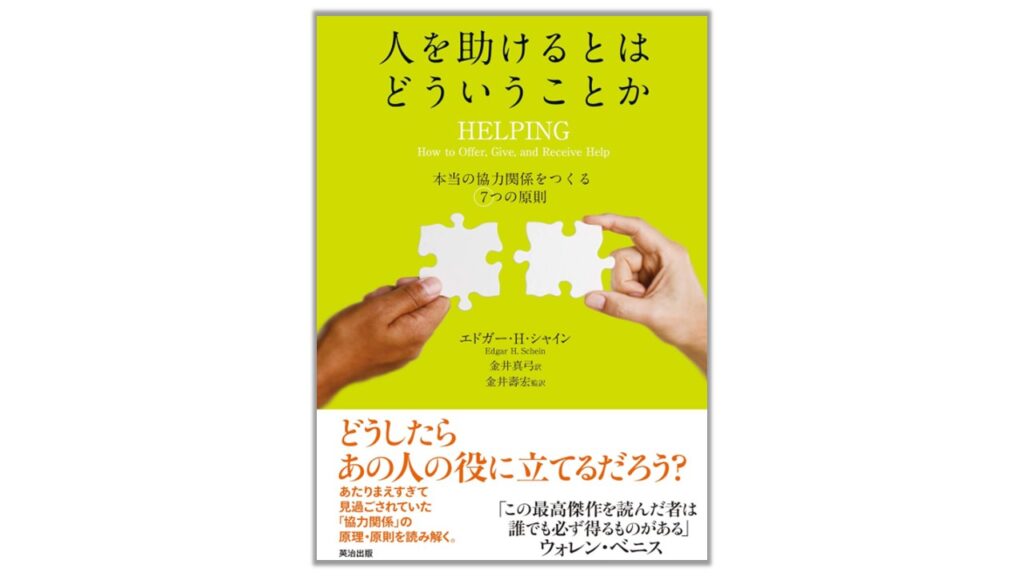心と向き合うときにおススメの本
-

人を助けるとはどういうことか
翻訳が、恐らく原文に忠実すぎて、理解するために大きなストレスがかかる。他の金井先生の著書を読んでも、文章が固すぎて読み進めるのに苦労している。組織心理学は自分の実務経験が大きい分野なのに、欲求と痛みが狭い家に同居してしている感覚だ。 それ… -


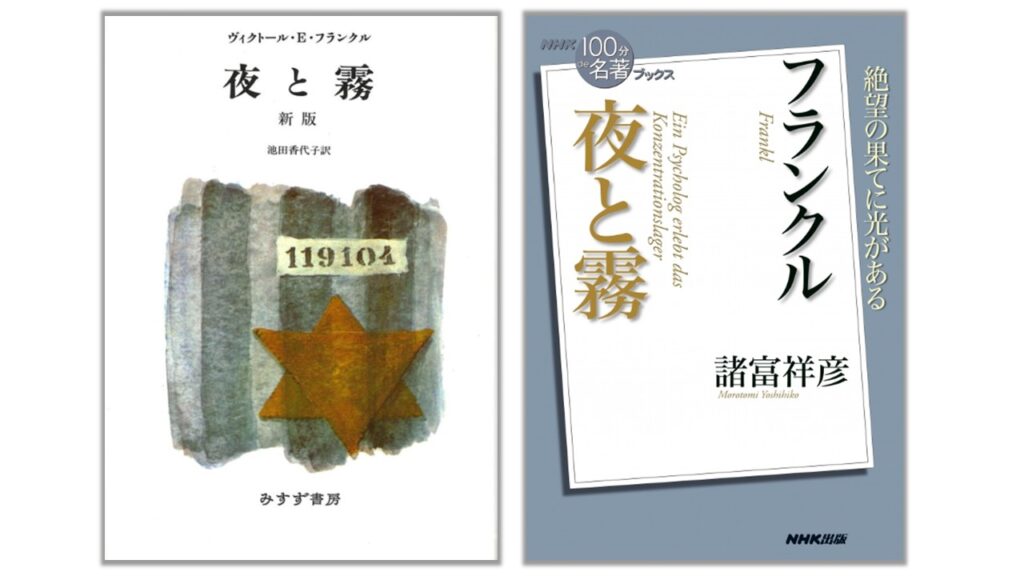
夜と霧
『夜と霧(新版)』の中では、ロゴセラピーについて直接説明されていないため、『100分で名著』を並行して読むことで、理論的な理解も深まったように思いました。私は次のように理解しました。 苦悩し、自分自身のかけがえのなさと責任の重さに気づくこと… -


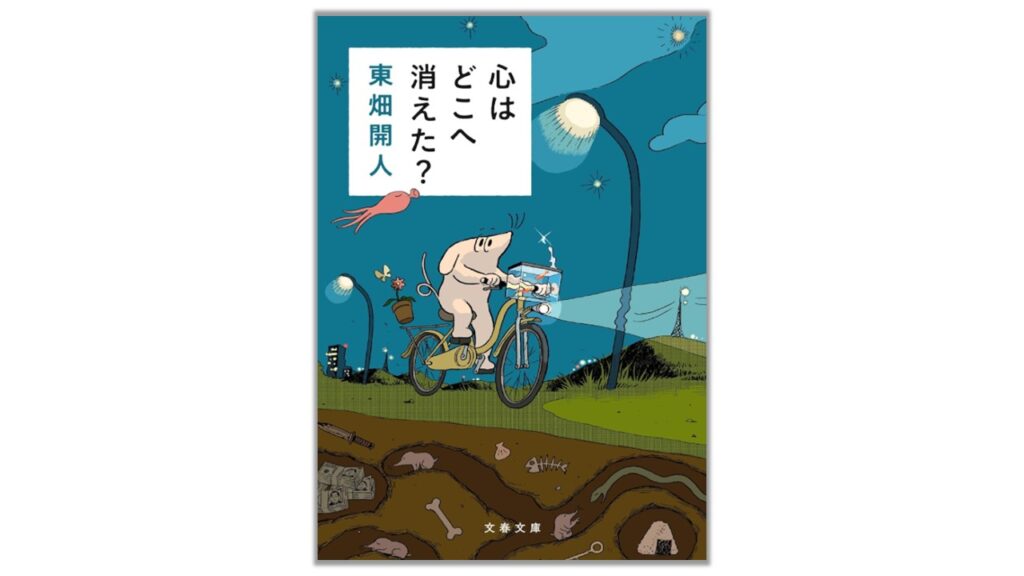
心はどこへ消えた?
なんだか、カウンセリングを受けた後のような、すっきりした気持ちになります。今のままでいいですよ、とそのままの自分を認めてもらえたような。 軽快な文章の中にも、心理学やカウンセリングに関する鋭い視点もあって、読み応えがありました。 「心は変… -


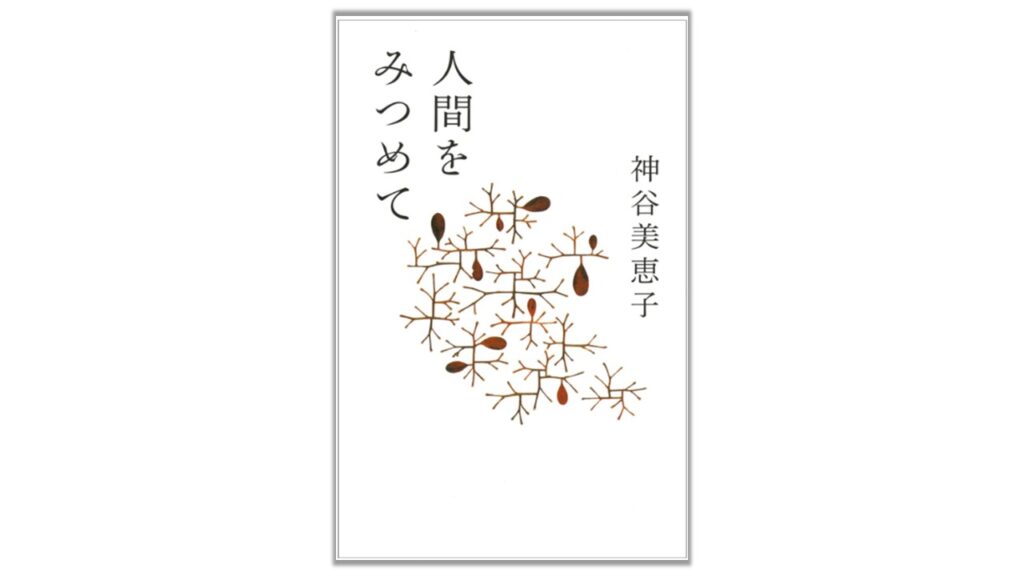
人間をみつめて
著者が障害者と接した多くの経験。そこから丁寧に語られる言葉は、時代を超えて自分の中のモヤモヤに目を向けさせてくれる。 優しく穏やかに自己と対話する時間を大切にしたい。同じくらいに社会の中で生きていることを忘れないでいたい。そして私が働けな… -


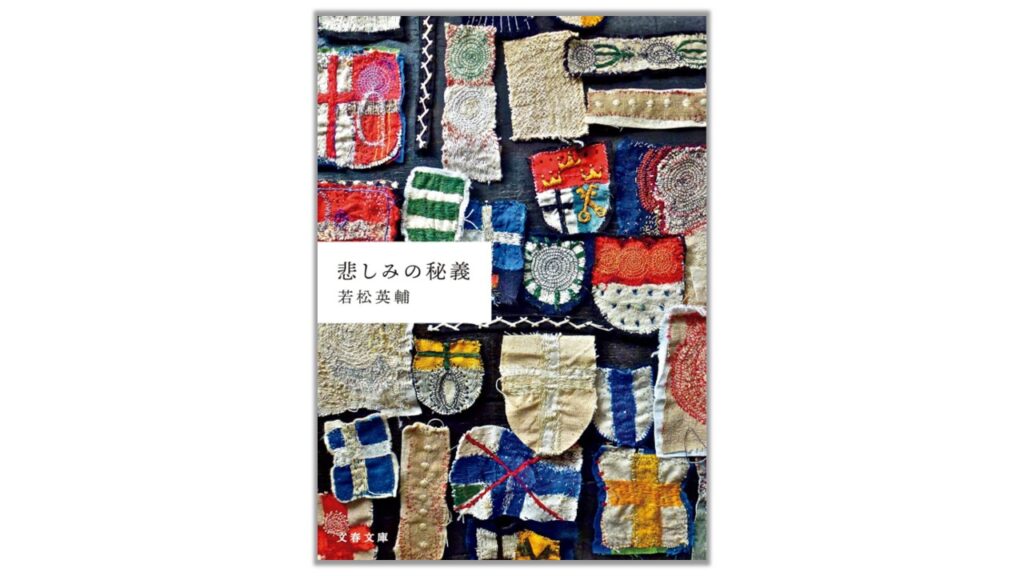
悲しみの秘義
フランクルと宮沢賢治の引用から始まり、お!と思う。 言葉のひとつひとつが丁寧に選ばれて重ね合わされていく。文章に強い重力を感じてページが進まない。書くことと読むこと、愛、病、悲しみ、死。テーマも重い。10ページに満たないエッセイが25編。大切… -


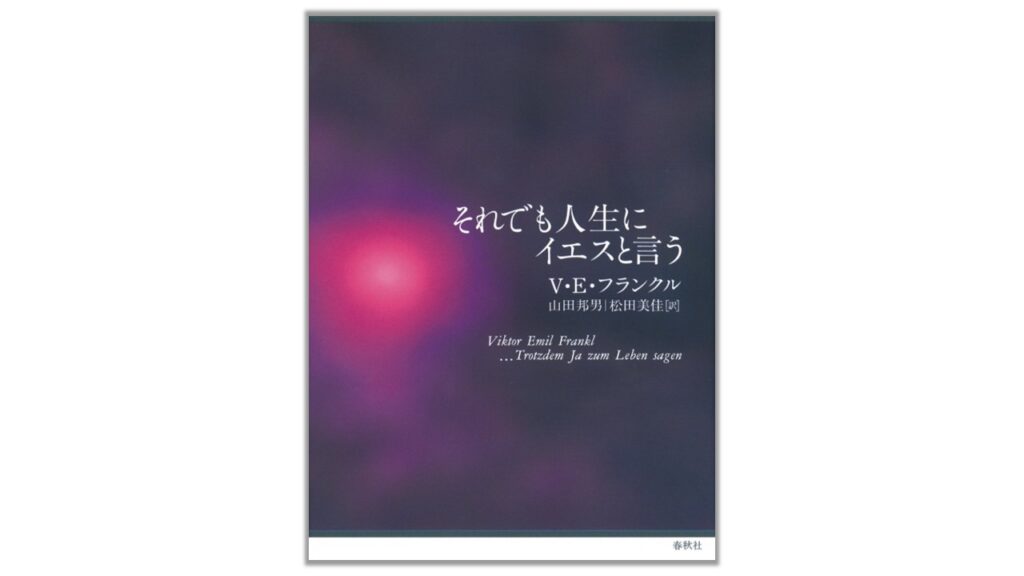
それでも人生にイエスと言う
社会の役に立たなくなっても、生きている意味はあるか。 自分にも差し迫ってくるこの問題に、自分なりの言葉をもっていたいと思います。 ナチスの強制収容所を出た翌年、フランクルはこう語ります。 「社会の役に立つということは、人間存在を測ることがで… -



嫌われる勇気
10年ぶりに読み返してみると、当時引っかからなかった言葉が気になっていることに気がつきました。たくさん出てくるキーワードのうち、今回気になったものをいくつか挙げてみます。日本キャリア開発協会(JCDA)の会員となりキャリアコンサルタントとして… -


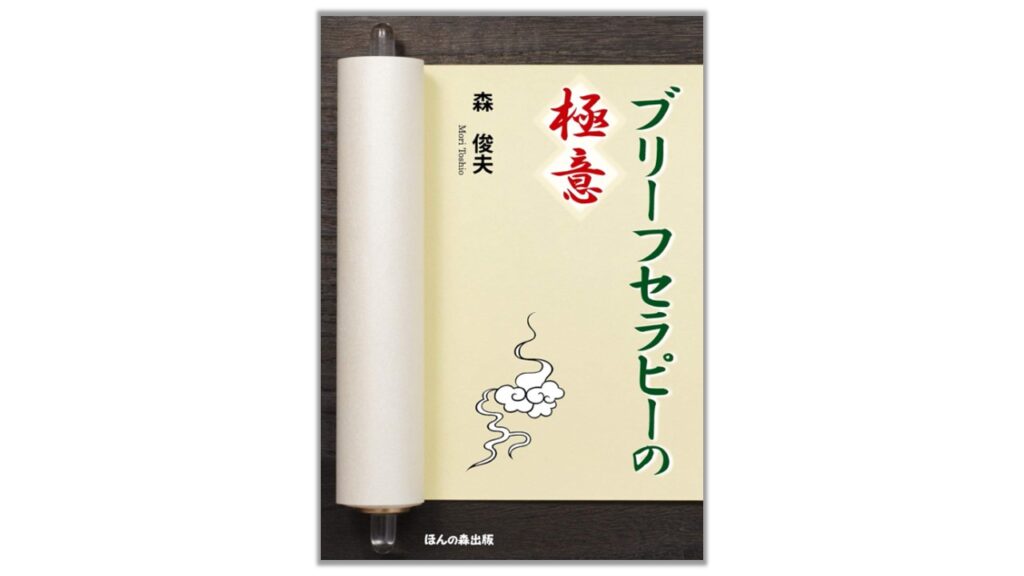
ブリーフセラピーの極意
ブリーフセラピーとは何だ? 自分の理解はこうです。 心理療法のひとつだから、治療方法のひとつであり、キャリアカウンセリングの手法ではない。でもブリーフセラピーの考え方がキャリアカウンセリングにとても役立つから取り入れたらどうかな、というこ… -


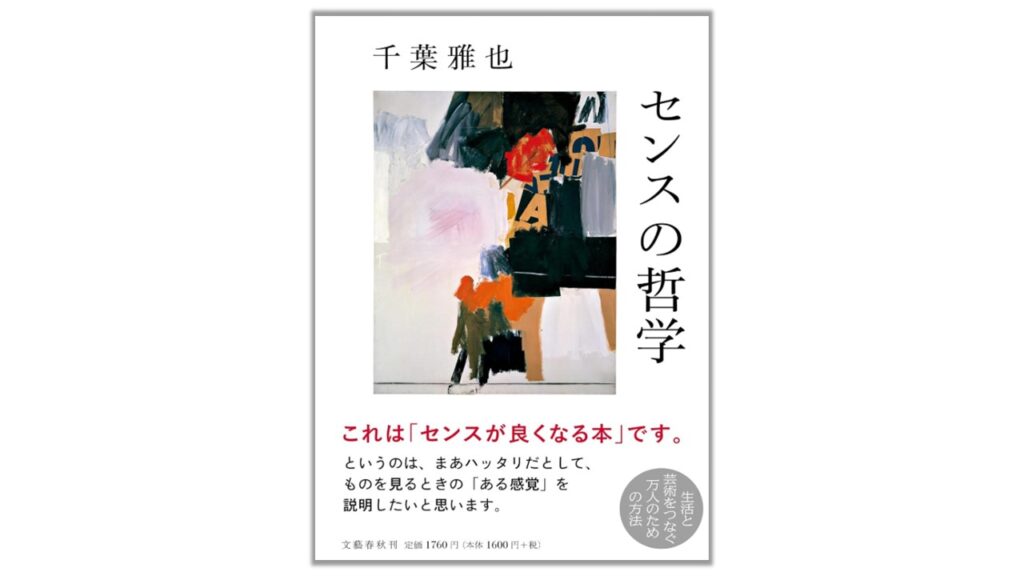
センスの哲学
絵画には意味はなくて、あるのはリズム。だから絵画は音楽と同じ。 こんな考え方に衝撃を受けました。 「美術も音楽も、映画も小説も、何かの次に何かが来る、という並びが重なり合った「うねりとビート」である」 (168ページ)、さらに「ポークソテーのマ… -


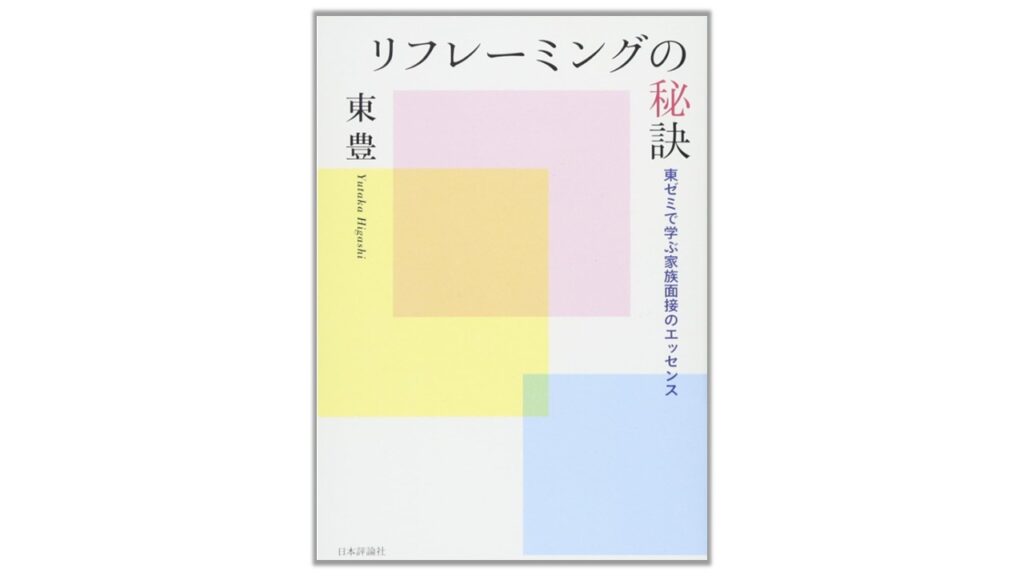
リフレーミングの秘訣
著者と学生との議論がたくさん掲載されていて自分も一緒に学んでいる気分になります。平易で嫌味がないのが好印象です。 基礎知識に加え、4つの事例とその解説、議論を通して、理解を深めることができます。 特に著者はポジティブリフレーミングを推奨して… -


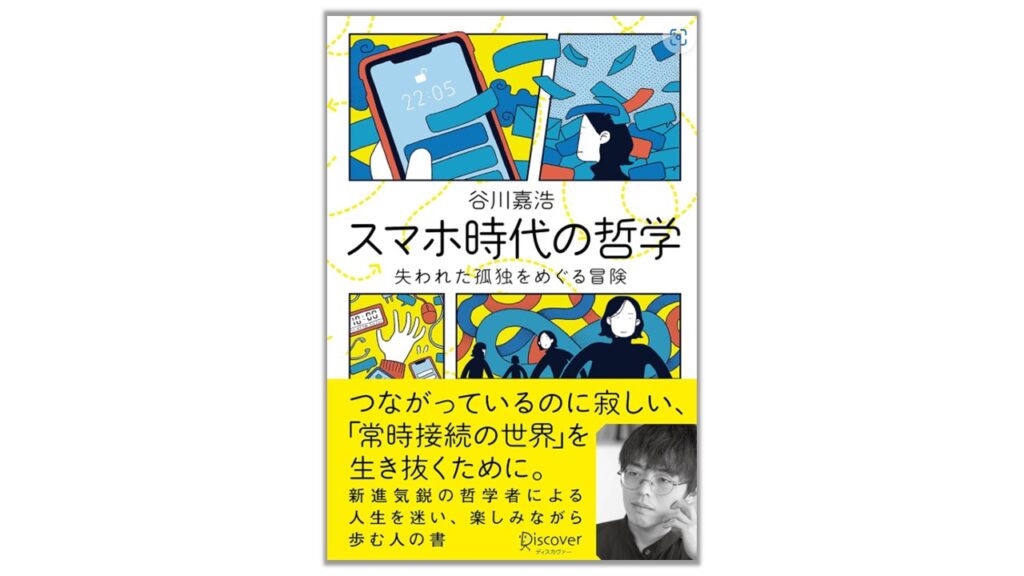
スマホ時代の哲学
スマホ依存、マルチタスク、集中力欠如・・・という自分に仕方ないよね、と現状認識。ダメな自分に著者が寄り添ってくれます。 仕事をする自分、趣味の自分など、いろんな自分がつながっているのを感じます。 そして、情けなくて不完全な自分を認める勇気… -


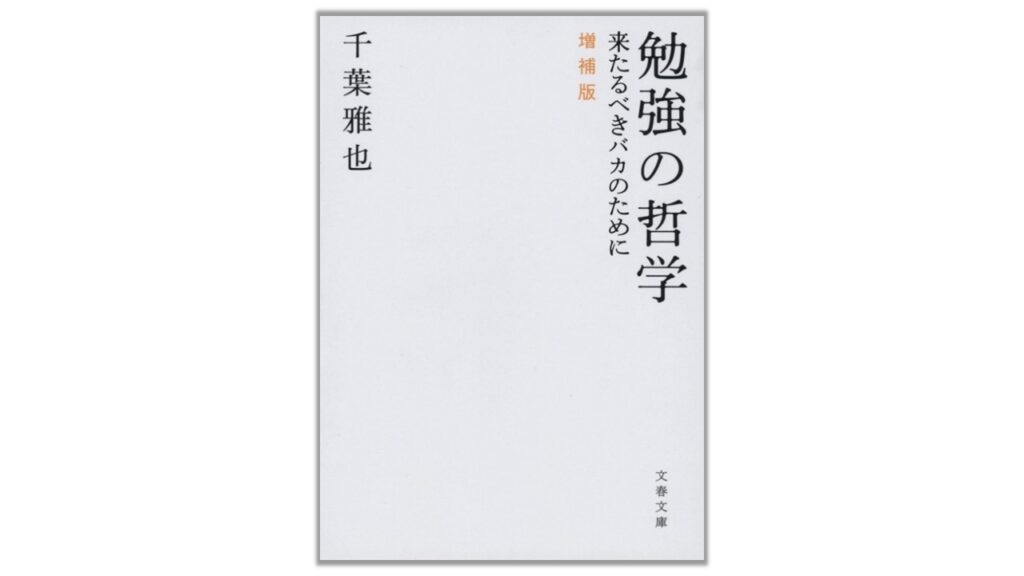
勉強の哲学
「勉強とは自己破壊である」 ここで言う勉強とは、今までと違う分野を学ぶこと、つまり、リスキリングとか、転職とか、職種変更とか、身近な例で言えばそういうことでしょうか。 長いつきあいの同僚たちと、同じ「ノリ」でテンポよく仕事をしている、そん… -


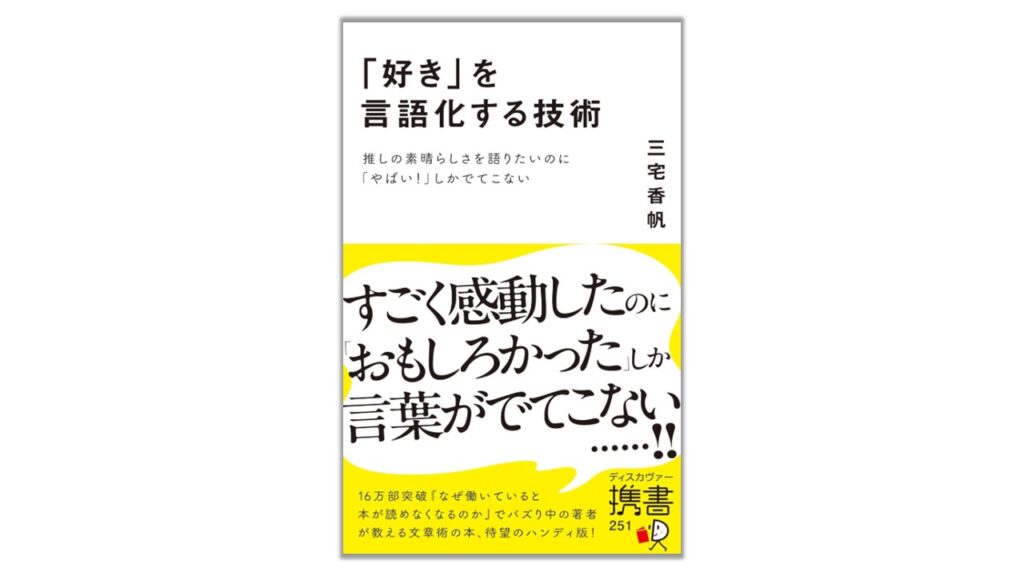
「好き」を言語化する技術
人気書評家が「書くこと」についてまとめた本の感想を述べるのは、ちょっと勇気が必要でした・・・ですので、第5章で著者がすすめている「見出しをつける」という修正方法を使ってまとめてみました。 私の感じた「よかった!」こと3つを整理してみました… -


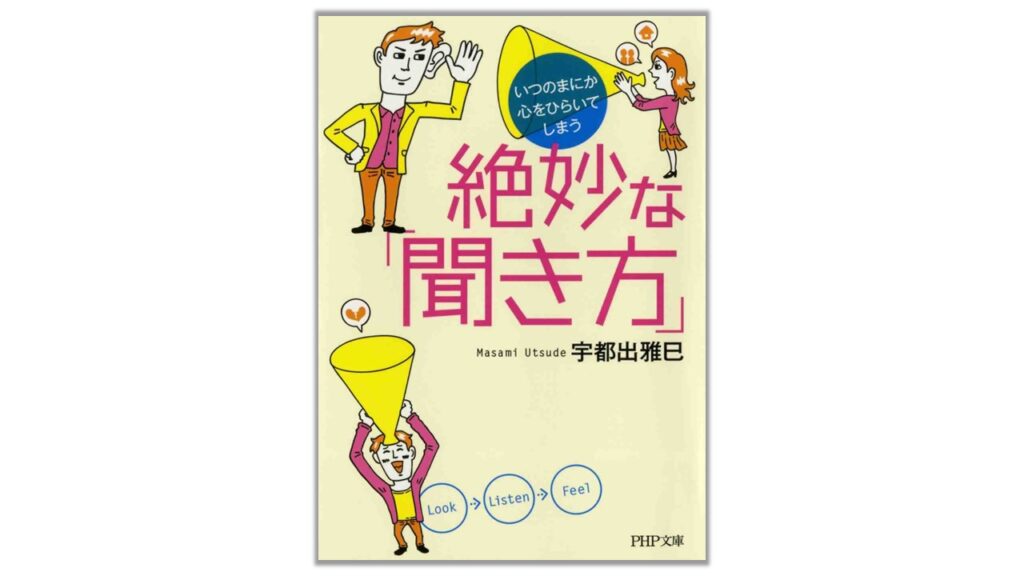
絶妙な「聞き方」
本の中で紹介されている技術は、かわいいイラストとともに紹介され、やさしく理解できます。 「人の話は中断しなさい!」という話は、キャリアコンサルタントとしては「え!?」と一瞬思うのですが、なるほどと合点がいきます。 世の中のみんなが聴く技術を… -


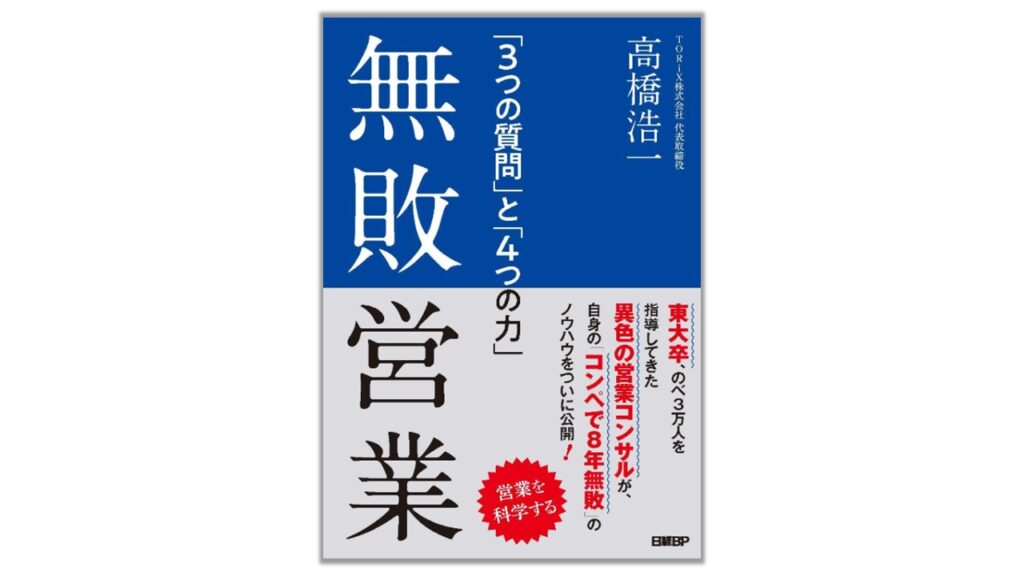
無敗営業
「営業力は技術だから、誰でも身につけられる」と著者は言うものの、簡単ではないでしょう。 効率よくその「技術」を身につける方法は、この本から学ぶことができます。職場のメンバーで具体的な「やっちまった~」という経験を共有するのも組織の一体感を増し、… -


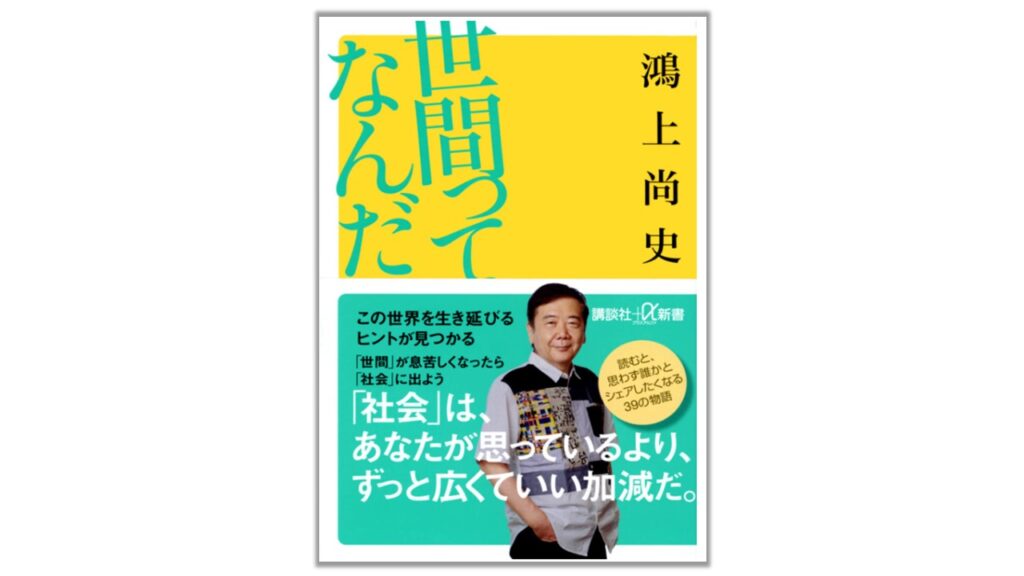
世間ってなんだ
鴻上尚史さんの「世間論」は、自分の「世間」を当てはめて考えるとわかりやすい。 35年間、会社員として同じ会社に所属していると、生温かい「世間」に囲まれていたのだろうなぁと思います。企業の中の組織は究極の「世間」かもしれない。 さあ定年後はど… -


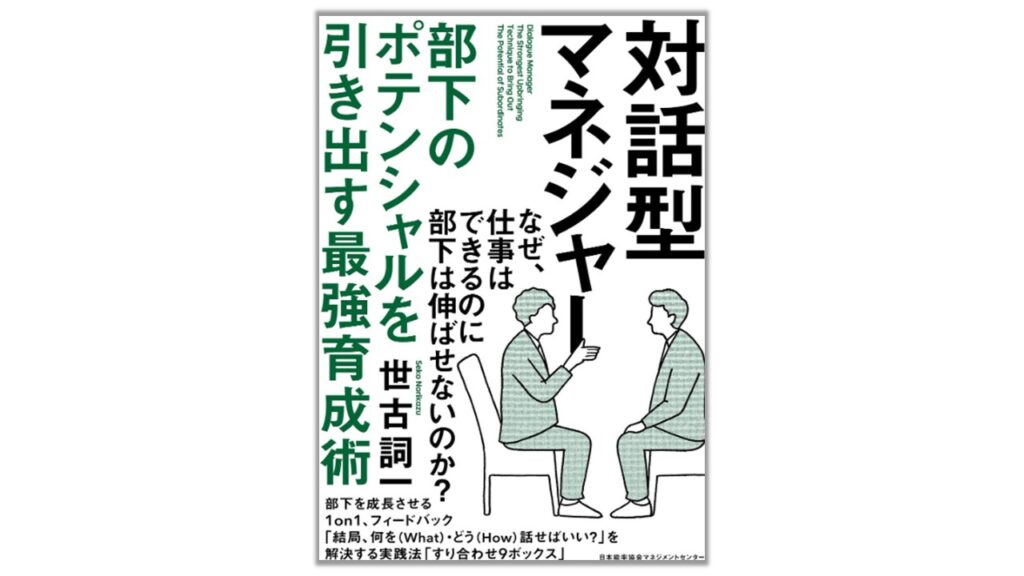
対話型マネージャー
1on1で何を話すか。業務/個人/組織と、過去/現在/未来のマトリックスで「すり合わせ9ボックス」として分類、具体例を示しています。具体的な会話例も多く掲載されていて実践がイメージしやすく「これならできるかな」と感じれるかも。 1on1を定期的にやり… -


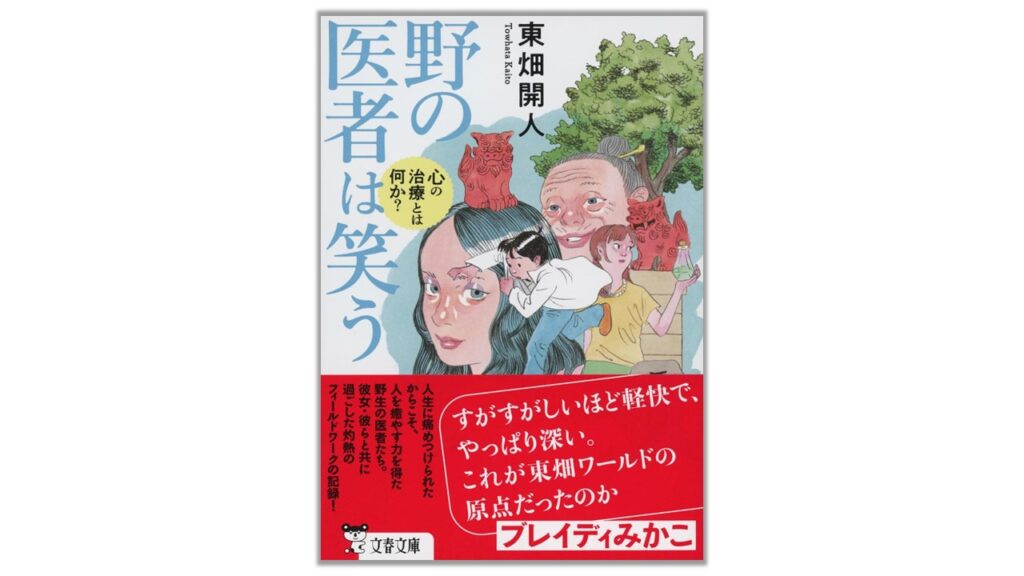
野の医者は笑う
心の治療とは?野の医者とは?臨床心理学とは? 私にとって臨床心理学は未知の世界だけど、そうかと言ってヒトゴトでもない。野の医者を知ることによって、自分の身の回りで起こるいくつかのコトについて、気持ちの整理がつきました。それは、スピリチュア… -


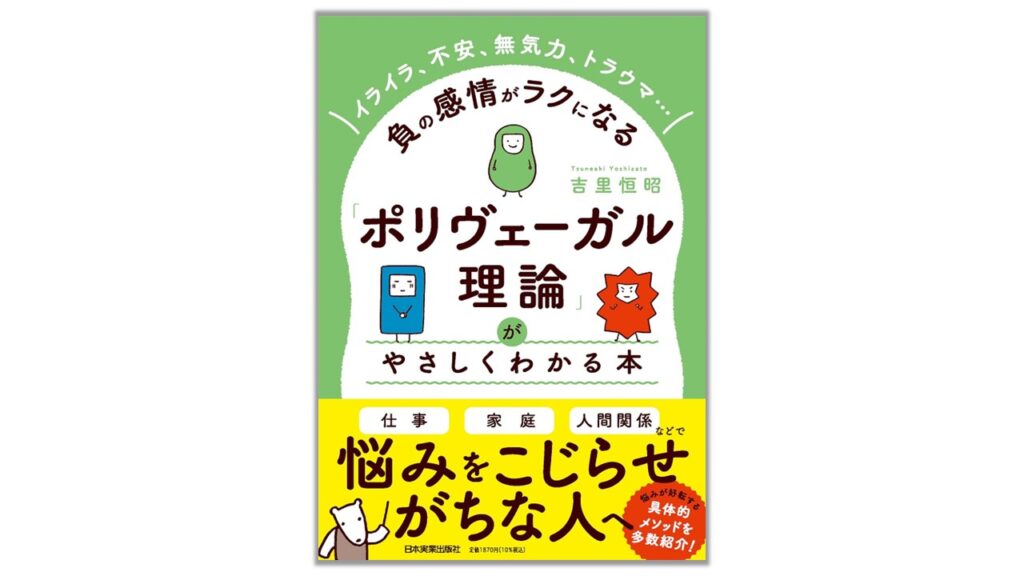
ポリヴェーガル理論がやさしくわかる本
癒されます、このキャラクター。 自分の中に赤さん、青さん、緑さんがいるんだなと思うとほっこり。 「心を治さないと」「私の性格が悪いから」「努力が足りないから」と考えるより、自律神経がアンバランスになってるなー、って考える方が気楽に生きられそうで… -


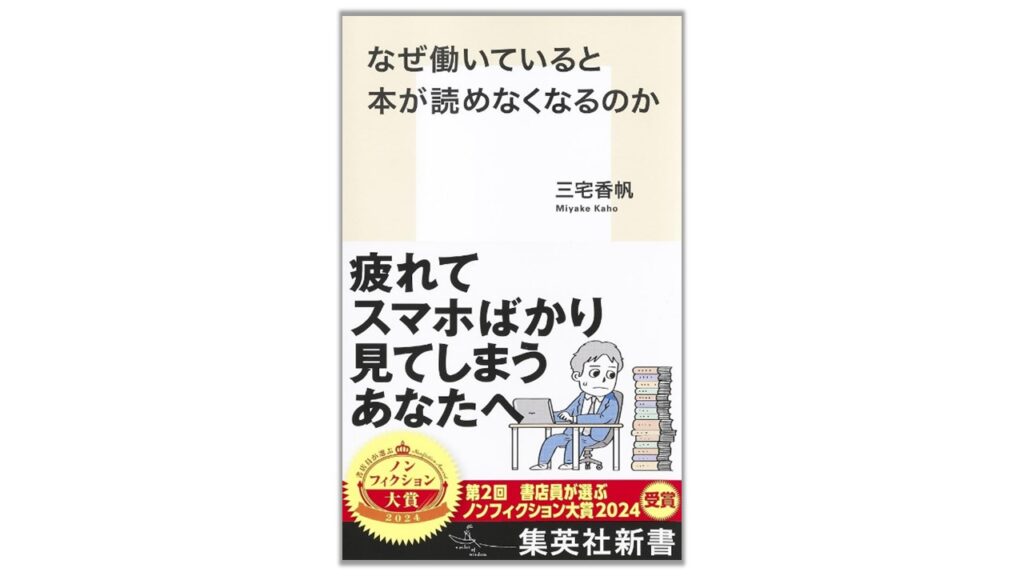
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
三宅香帆さんのトークセッションが勤務先で開催されると聞き、本棚に放置されていた著作、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を慌てて読んだらとても面白かった!最後はなぜか、じーんときた。 トークセッションから著者の人柄も垣間見えたことでな… -


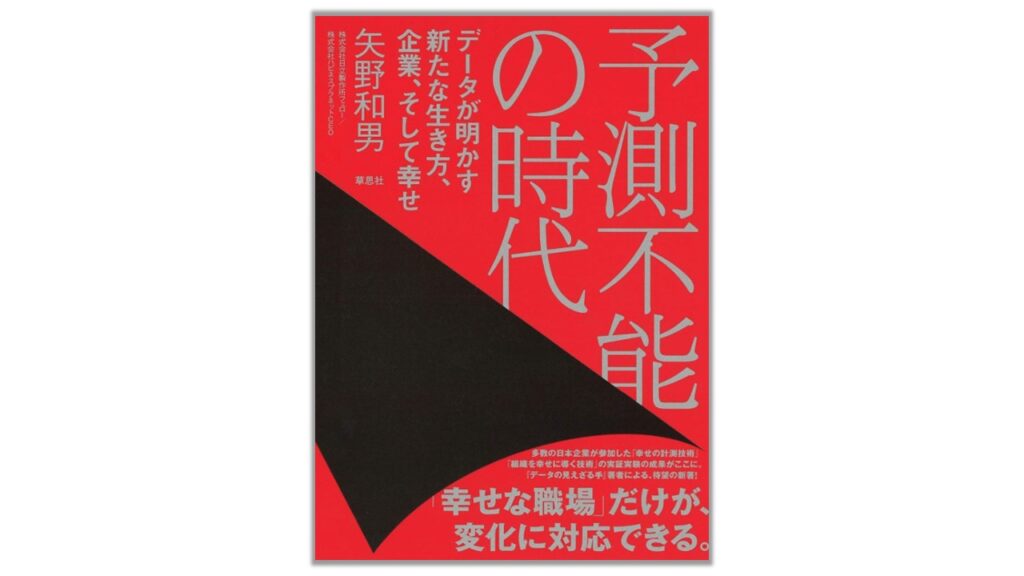
予測不能の時代
先日勤務先で矢野氏のウェルビーイングに関するセミナーがあり、興味を持って本書を購入しました。 予測不能の時代で鍵になるのは、「幸せ」だという。ここでは幸せを血管・筋肉・呼吸などの生化学の変化と捉え、データを解析することで幸せな組織を「FINE… -


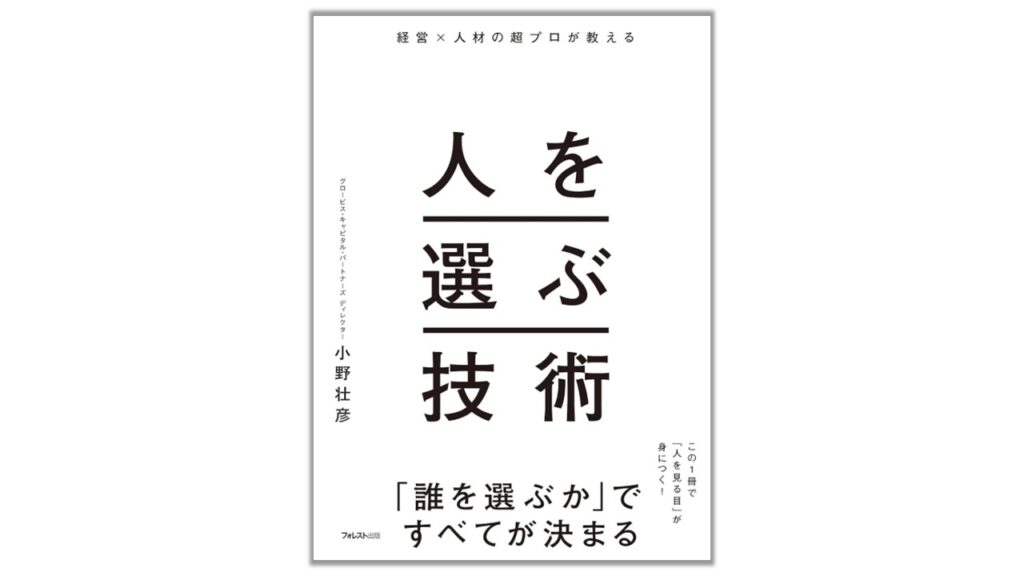
人を選ぶ技術
「人を選ぶ」なんてお前何様だと自分をなじりながら、あるところで推薦図書になっていたので手に取りました。 「森喜朗はなぜ失言するのか?」という話と、こうした失言癖のある人を重要なポストに起用すべきでないのか?という話は大変興味深い。また、面… -


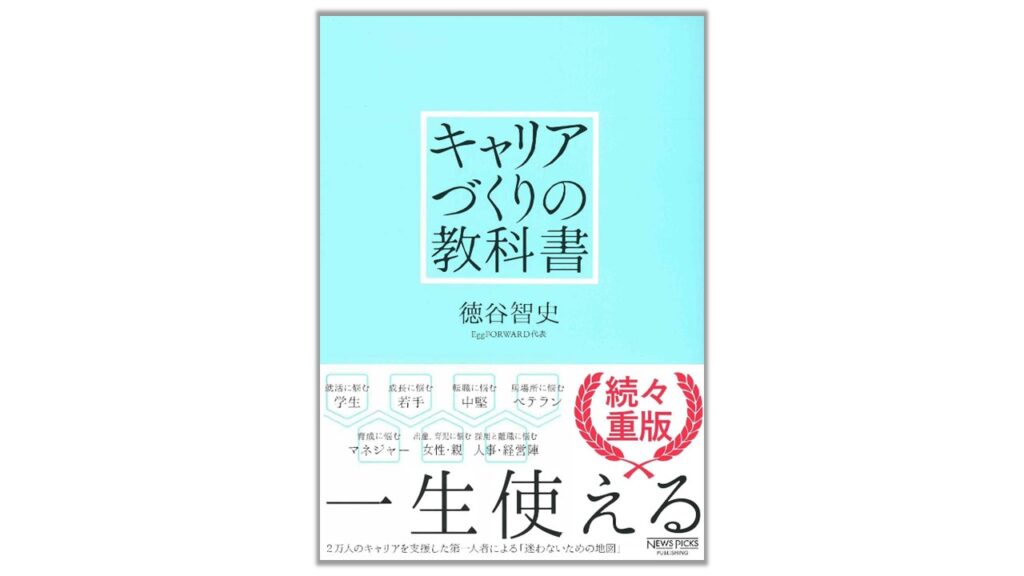
キャリアづくりの教科書
とても好印象の「教科書」です。厚さの割にはスイスイ読めて気持ちいい。 理由の1つ目は、全体的に主張が片寄っていないことです。著者の知識と経験はすごいものを感じますが、それを強要することなく読者の理解に任されています。「キャリア選択のあり方… -


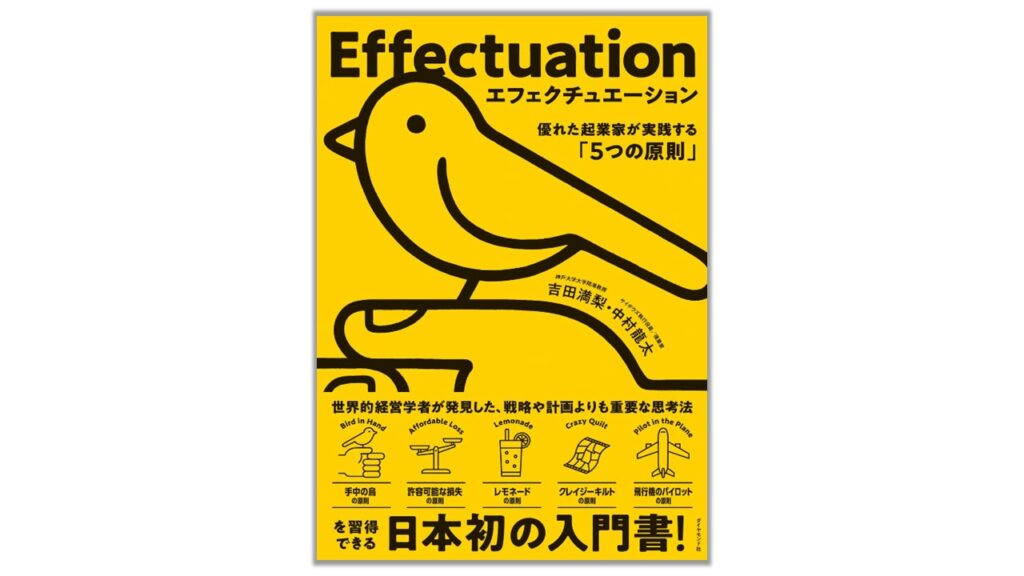
エフェクチュエーション
エフェクチュエーションとは、 「高い不確実性に対して予測ではなくコントロールによって対処する思考様式」 です。 従来の「目的主導」でリスク予測を重視した「コーゼーション(causation:因果論)」と対をなす考え方です。 起業家が新規事業を立ち上げ…