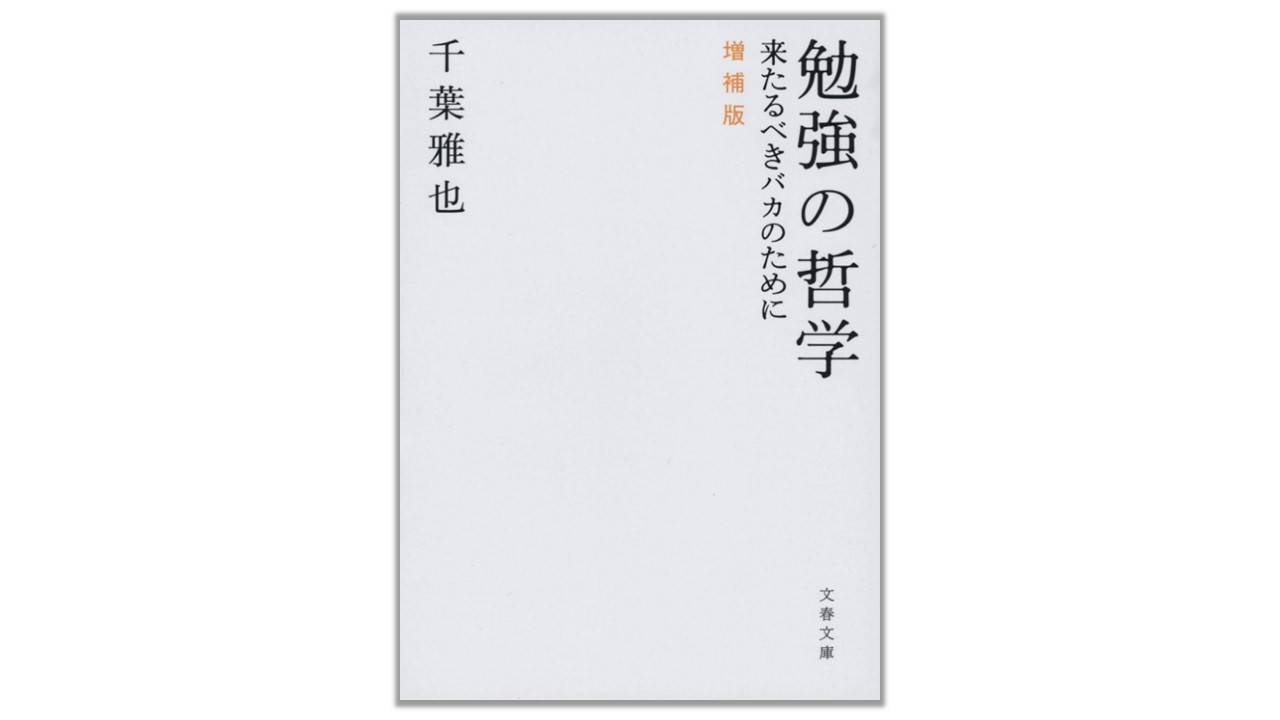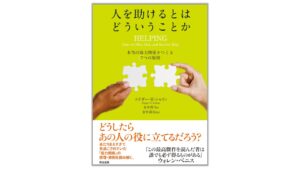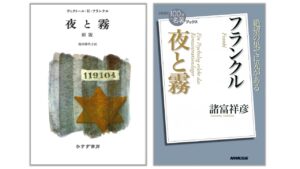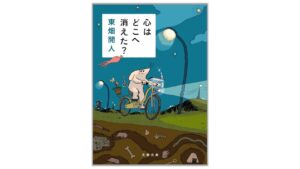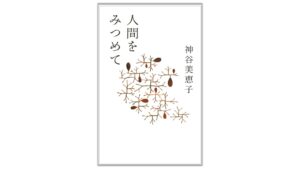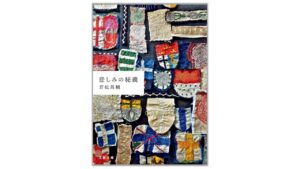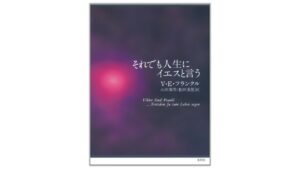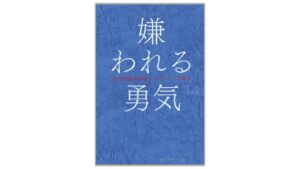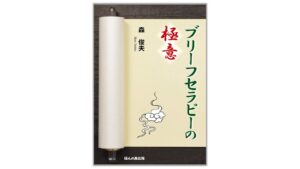「勉強とは自己破壊である」
ここで言う勉強とは、今までと違う分野を学ぶこと、つまり、リスキリングとか、転職とか、職種変更とか、身近な例で言えばそういうことでしょうか。
長いつきあいの同僚たちと、同じ「ノリ」でテンポよく仕事をしている、そんな環境から抜け出て別の世界に飛び込む。いままでの自分をいったん脇に置いて、私の場合だと「この言葉遣い違和感ある~(泣)」とか「頭に沁みこまないで跳ね返っちゃう!(怒)」とか感じながらも立ち向かっていく。この時に大切なのが「言語」。通常言語は「現実」と結び付けて「道具」として思考したり行為したりしているけれど、「玩具的」に使ってみる。言葉をおもちゃのように使って、周囲の「ノリ」から浮いてみる。周囲から「キモい人」になってみる。深く勉強すると、こんな状態になると私は理解しました。
同調圧力。近年少なくなってきたように感じます。それでも「私は私なんで」と仲間から距離を置くのは勇気とパワーが要ります。でも勉強って、若い人はもちろん歳を重ねれば重ねるほど大切になりますね。歳とともにぬるま湯に浸ったままでいたくなるから。
「信頼に値する人は、粘り強く比較を続けている人である」という著者の言葉には励まされます。なんでもぱっぱと結論を出しさえすればよいというものでもない。自分なりのこだわりを大切にしながら「仮の結論」を出して前に進む。今までの思考を無にするような「決断主義」に陥らない。ネガティブケイパビリティの考え方にもつながり、私としてはしっくりきます。
後半は具体的な勉強の仕方、本の使い方にも言及していますが、私としては前半の勉強論の方がそそられます。
千葉雅也さんの本は語りかけるような優しい文章でとても好感が持てますが、中身は濃くて奥深いように思います。
勉強の哲学 千葉雅也著
文春文庫
2025/1/12